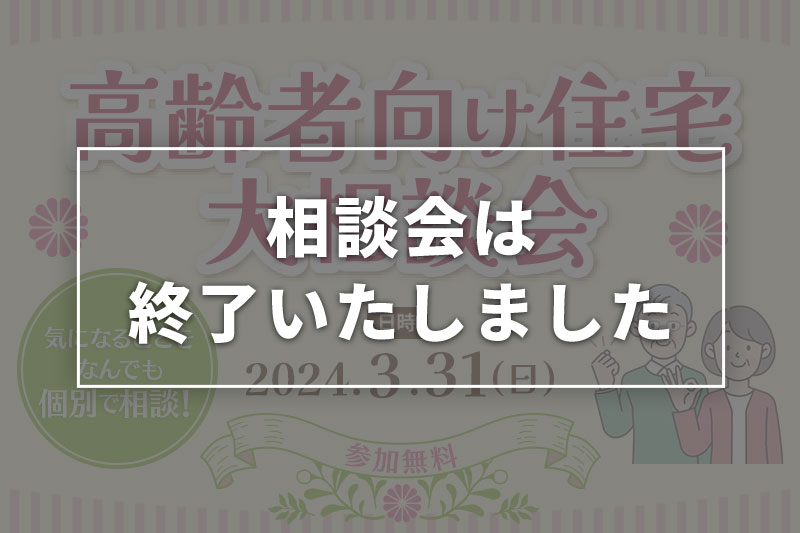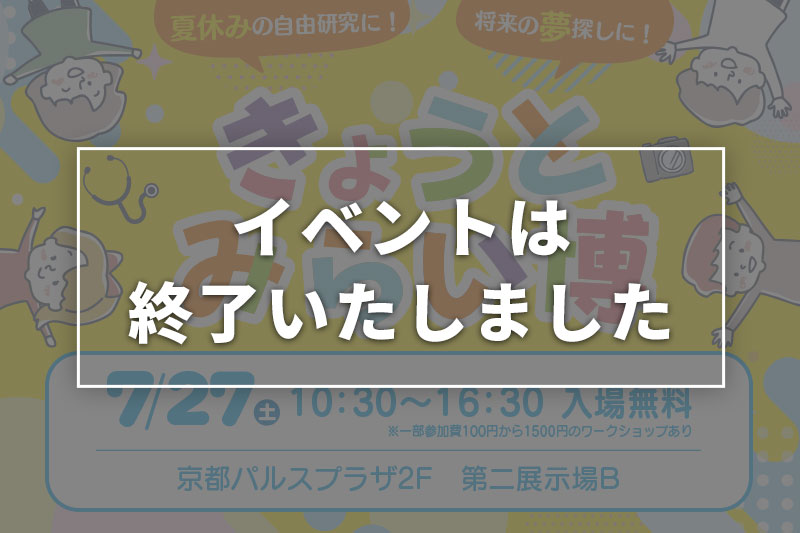京都の夏を感じる、さまざまなもの。その背景にあるのが職人の技です。製造の現場を訪ねました。
撮影/桂伸也
分業制の困難を乗り越えて守る京うちわ
塩見団扇(山科区)

「中骨とは別に作る柄を後から差し込むのが、『京うちわ』の特徴です」と話すのは、「塩見団扇(だんせん)」の秋田悦克さん。伝統的な京うちわをはじめ、最近では和のデザインのもの、洋室に飾っても似合うものなど、多様なうちわを製作しています。
「山鉾巡行はなくても、祇園祭の時期にうちわを配りたいという依頼も多いので、6月中に納品できるよう作業しています」(取材時は5月下旬)
職人の一人が進めていたのは、竹骨に和紙を張る〝合わせ〟。板にのりを延ばし、竹骨をその上に。竹骨にのりが付いたら和紙を重ねる…、この工程を繰り返します。「受注数にもよりますが、注文が増える夏前は、1日300枚くらい張っています」とのこと。
さらに、うちわの縁に細長い紙を張る〝へりとり〟、柄を付ける〝柄差(えさし)〟も行われていました。細かい作業が多いため、集中力が必要です。
「昔は分業制で竹骨や柄だけを作る職人がいましたが、後継者不足で廃業。多くの作業を自社でまかなうようになりました。京うちわは京友禅、襖(ふすま)絵といった京都のさまざまな職人の技が組み合わさり、装飾品としても発展してきた工芸品。文化が廃れないよう、洋室に合う商品も作ったりと工夫しています」
使ってみてください、と秋田さんから手渡された京うちわ。少しあおぐだけで、涼やかな風が感じられました。


青々とした竹に手をかけ生まれる一輪挿し
高野竹工(長岡京市)

辺りを囲む、爽やかな竹。訪ねたのは長岡天満宮隣にある「竹生(ちくぶ)園」。竹や木材を使った製品を手掛ける「高野竹工」の、工房兼ショールームです。
「自社で管理している竹林から年間1500~2000本の竹を使い、さまざまなアイテムを作っています」と、取締役兼企画営業部部長の西田隼人さん。
指物、蒔絵(まきえ)、漆塗りなどの職人24人が在籍。竹を使ったアイテムが夏に人気です。竹工芸が専門の野崎博之さんが作っていたのは、竹の一輪挿し。
まずは短くカットされた竹に、小型ののこぎりで花を生ける場所に切り込みを入れます。
「竹は少し反った形をしているので、真っすぐに見える向きが正面になるよう、花を生ける穴の位置を決めるのが大切です」(野崎さん)
大方を切ったら、切り込み部分をなたでトンッと割って穴開け。続いてナイフを取り出し、竹を削って形を整えていきます。仕上げはやすりがけ。この後、別の職人によって蒔絵が施されたり、金箔(きんぱく)が貼られたりと装飾が加わることもあるそう。
「最近は地域の人を集めて竹を使ったワークショップも開催。竹の魅力を広く伝えていきたいです」(西田さん)


一瞬、一瞬を大切にして作るくずきり
鍵善良房(東山区)

賞味期限は15分―。祇園四条にある「鍵善良房」のくずきりを食べることを、夏の恒例にしているとの声も聞きます。
「材料は吉野本くずと水のみ。食感も見た目の透明度もすぐ変わってしまうので、注文を受けてから作り、出来たてをお出ししています」と、同店総務担当。
「夏は例年、常に職人たちがくずきりを作り続けている状態です。火を使うので暑さが厳しいですが、交代しながら励んでいます」
取材では職人歴4年、千葉洋海さんの仕事を見せてもらいました。
製法は昔から変わらず。まずはくず粉と水を混ぜ、1人分を平らな銅鍋に入れて湯煎にかけます。「くずの厚さが均等になるように鍋を回していきます。先輩から教わりましたが、最初はなかなかうまくできませんでしたね」(千葉さん)
「次はちょっと不思議なことが起こりますよ」と総務担当。鍋ごと熱湯につけると…、白かったくずが一瞬で透明に!
素早く冷水につけて鍋からくずをはがし、まな板の上へ。粘り気があるため、中華包丁で〝たたき切る〟のがポイント。千葉さんがリズムよく切り、出来上がりです。
二段重ねの信玄弁当風の器は、昭和初期に芝居小屋などに出前をしていた名残。昔から変わらない味が今も楽しめます。


「ちょうちんだけでも」との思いに応えて今年も
髙橋提燈(下京区)

5月下旬、「髙橋提燈」の山科区の工場では、職人たちが夏祭りや地蔵盆などのためのちょうちん作りの真っ最中。あちこちに、製作途中のちょうちんが置かれていました。
営業部の丸山弥生さんによると、「年間約5000~6000個を製作しています」。浅草・雷門のちょうちんも手掛ける江戸時代中期創業の同社では、現在15人の職人が働いています。
職人の一人が行っていたのは、竹骨に和紙を張る〝紙張り〟の作業。竹骨に、はけで手早くのりをつけていきます。次に登場したのは霧吹き。「水を吹き付けて和紙をやわらかくすると、きれいに張れるんです」と教えてくれました。
その後は、「絵付け」や「文字書き」の工程。地蔵盆用に「南無地蔵大菩薩」と書いたり、極彩色の図柄を描いていたりと、複数の職人が黙々と作業。「見本がある場合は模写。全てのちょうちんが同じ仕上がりになるよう、集中して仕事をしています」と話します。
「祇園祭や地蔵盆といった夏のちょうちん作りは、毎年3月ごろから始まります。祭りをしづらい今、『ちょうちんだけでも飾りたい』との声も。神様への明かりが、多くの人の心の〝ともしび〟になればと思います」(丸山さん)


リズミカルな作業を経て美しいすだれに
みす武(中京区)

カラカラカラ…と響く、リズミカルな音。竹を細く割った〝竹ひご〟を編み、すだれが作られていきます。
1741年の創業以来、翠簾(みす)やすだれを製造する「みす武(ぶ)」。翠簾はすだれの高級品。平安時代から宮中などで目隠しや間仕切りのために用いられてきました。
「夏は軒先に掛ける日よけ用のすだれはもちろん、お盆前に仏間用を新調したいという依頼も多いです」とは大久保武さん。代々「大久保武右衛門」を襲名していて、大久保さんは10代目です。
竹ひごを編んでいたのは、娘の和佳(まどか)さん。片手で竹ひごを押さえながら、糸を巻きつけた重りをヒュンヒュンと前後に投げていく様子(写真左下)はなんともスピーディー。カラカラ…という音は、このときの重り同士がぶつかる音なのです。
「竹の節をそろえて模様になるように編んでいます。ペースは1日25cmほど。真っすぐ編んでいくのが難しいですが、編み目が均等になるよう注意して取り組んでいます」(和佳さん)
編み上がったら西陣織の金襴(きんらん)を縁に。最後に房、金具を取り付けて完成です。
「近年はサイズや縁の種類など、オーダーメイドで製作。マンションが増えてすだれの需要も減りつつありますが、伝統と技術を守っていけたら」(大久保武さん)


(2021年7月17日号より)
最新の投稿
おすすめ情報
- カルチャー教室
- アローズ
- 求人特集
- 不動産特集
- 京都でかなえる家づくり
- 医院病院ナビ
- バス・タクシードライバー就職相談会in京都
- 高齢者向け住宅 大相談会
- きょうとみらい博