外観からでは分からない その歴史、その技術
街角や住宅街に立つ一軒。「何かの商売をしているようだけど」「ごく普通の住まいに見えるけど」―。実はそこで、伝統的な仕事がされていることもあるのです。今回は、外観からはうかがいしれない〝匠(たくみ)〟の仕事について紹介します。歴史と技術が、京都の街のあちこちに息づいています。
着物文化も支える、京都市では1軒だけの絹糸の加工場
小林練染(れんせん)工場 上京区

着物の町、西陣で100年以上。表の壁は4年前に塗り直したそうですが、瓦は昔のまま残されました

建物の東側から見た様子。精練機から伸びた大きな煙突が、唯一の工場らしさかも

原糸のセリシンを洗い流すための精練機。熱湯が流れるため、蒸気が立ち上っています。「この機械が導入される50~60年ほど前までは、大きな釜で原糸を煮ていました」と小林さん(手前)
約束の時間に「小林練染工場」を訪れた記者。玄関の前に立ってみても、工場であることを示す看板などは見当たりませんが、中に入ってみると奥の庭まで見渡せる広い作業場が。
「看板をかけたからといっても、小売りはしていませんし、通りすがりの人が入ってこられる仕事場でもないので」とは11代目の小林昭夫さん(66歳)。
ここ、西陣にある創業100年を超える「小林練染工場」では、絹糸を染色する前の〝精練(せいれん)〟という加工を行っています。現在、こうした専門の工場は、京都市ではこちらの一軒のみだそう。工場名は精練から一文字、先代が染めをしていた時代の名残りの一文字が入っています。
絹糸の精練とは、小林さんによると「洗濯のようなもの」。カイコのまゆから取り出した絹の原糸はセリシンという乳白色の成分でコーティングされた固い状態なので、専用の石けんなどで洗い流し、光沢のある絹糸に仕上げるのです。
〝洗い流す〟とひと口に言っても、〝全練り〟〝半練り〟〝三分練り〟など、その度合いによって風合いや用途が変わるのだとか。専門の工場だからこそ多様な要望に応えられるとあって、着物や帯、洋服や化粧筆などを扱う全国の業者から注文が入ります。
寒さも暑さも…、作業は厳しい環境で

精練後は脱水機に。精練機から大量の糸を運んで、詰めて、取り出して。水分を含んだ糸の束は重量があり、なかなか大変な作業です

脱水後は、金属製の棒を使って糸の束をなめらかに整えて干す〝整理〟という作業。アクセサリーはもちろん、ボタンやファスナーの付いた服も糸がひっかかるのでNGだとか。天井には整理された糸が干されています
ところで工場内は、外にいるのと同じくらいの寒さ。ダウンジャケットを着て作業している人もいるほどですが、これは表の戸が開け放っしだから。熱湯で原糸を洗う際に出る蒸気がこもらないようにするためと、脱水後に干す過程で糸がしっかりと乾くよう風通しをよくするためなのだそう。
この寒さを我慢しても、冬場は乾燥に3日ほどかかるのだとか。夏ももちろん、冷房などはありません。こうした作業を、家族を含めた4人の従業員で行います。
小林さんは、「この仕事を始めて44年、ここで生まれ育って、継ぐのが当たり前だと思っていたので好き・嫌いという感情はありません。でも、誇りを持っているのは確かです。今後、伸びていく仕事ではないかもしれませんが、日本の文化や京都の着物文化に根付いているので絶対に必要だと思っています」。

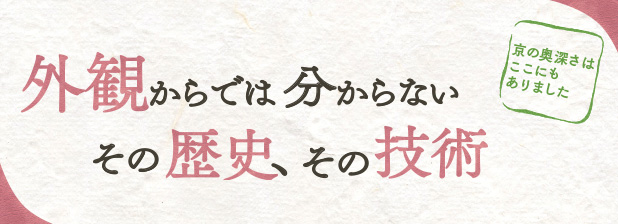
 ひと
ひと 食
食 健康・美容
健康・美容 おでかけ
おでかけ ファッション・雑貨
ファッション・雑貨 社会・生活
社会・生活 子育て・子ども
子育て・子ども 人間関係
人間関係