普段何げなく歩いている地面。今回はその下、そう、〝地下〟に注目してみました。日常では、なかなか目にする機会がない場所には、「そんなふうになっていたの?」という驚きも。京都の町の見方が少し変わるかもしれませんね。

発掘作業は、数カ所に分かれ、同時進行で行われていました。不要な土はベルトコンベアーにのせて、作業の邪魔にならない位置まで運ばれます
京都の町を掘ると、何かが出てくる─。こんな言葉を聞いたことはありませんか? では、いったい京都の地下にはどんなものが眠っているのでしょう。
それを調べるために訪ねたのが、普段は公開されていない発掘調査の現場。河原町丸太町の北西角にある元春日小学校です。
「江戸時代末期から明治の初めにかけて、生蓮寺と公家屋敷があった場所です」とは、発掘調査を行う京都市埋蔵文化財研究所の吉崎伸さん。
「京都の市街地は、平安時代以降ずっと人が住み続けています。昔はがれきや生活ゴミを処理する発想がなかったので、その場所に積み重ねて、整地していました。ゴミが何層にも重なっていると言えば分かりやすいかもしれませんね。今かかっている層の調査が終われば、さらに下層の、もっと古い時代の調査をします。土の色と質で違いを見分け、掘り進める箇所を決めていくんですよ」
1時間で、食器や丸瓦が次々と

池の中にあった飛び石の上に立つ吉崎さん。撮影後、池の隅から出土した2つのつぼを見て、「池の中で飼われていた金魚などの寝床だったのでしょう」と解説してくれました

これらの食器類は、全部同じ井戸から出土したもの。まんじゅう食い人形や灯火器のほか、公家の遊びに使われていたという犬やおいらんの人形もありました
作業をしている皆さんは、手慣れた様子でスコップなどを使い、不要な土を取り除いていきます。記者が滞在した1時間ほどの間にも、食器や丸瓦の一部が次々に出土。その正確な場所を記録係が図面上に書き込んでいきます。遺物は、一つ一つ番号が付けられ、どの場所からいつ出土したのか分かるようにした上で京都市埋蔵文化財研究所と併設の京都市考古資料館で管理しているのだそう。
ところで、大きなくぼみ(右写真)が見えますが、これは何ですか。
「池の跡ですね。しっくいで固めた土の上に水をはっていたのでしょう。当時の公家が屋敷からこの池を眺めていたかもしれません。そのほか、ここからは、かまどや井戸の跡も見つかっています」と吉崎さん。
見ていると、約200年前の生活がそこにあるように感じられ、なんとも不思議な気分になってきます。
「当時の生活実態を垣間みることができて面白いでしょう。記録をとれば土は埋め戻すので、こういった空間にいられるのはほんのひとときですが」
こうした発掘調査での出土品のうち、旧石器時代から江戸時代までの遺物や資料が展示されているのが京都市考古資料館です。展示物を見ることで、積み重なった歴史の上で生活していることを、あらためて認識するきっかけになりそうです。

京都市考古資料館の展示の一例。土師(はじ)器と呼ばれる土器で、形、大きさ、製作技法で年代が分かるのだそう

2014年、御幸町通竹屋町上ル毘沙門町近辺で出土。青銅に金メッキが施されたえび錠の一部で希少なものだそう。「倉庫の鍵だと思われます」(吉崎さん) ※一般公開はされていません

「キンシ正宗 堀野記念館」(中京区堺町通二条上ル)にある「桃の井」。「かつて、酒造りに使われていた名水が公開されています」(鈴木さん)
※「桃の井」の見学には入館料(大人300円)が必要です
「地下水は、大地からの恵み。神秘的な資源です」と話すのは、水の文化を研究しているカッパ研究会・世話人の鈴木康久さん。
京都では、古くから、名水と呼ばれる湧き水や井戸水が生活の一部として親しまれてきました。京都盆地の下には南北33キロ、東西12キロ、深さ800メートルの〝水がめ〟があるとされており、水量は約211億トンなのだそう。琵琶湖が水量275億トンとのことなので、そのスケールの大きさが分かりますね。
この水がめは、100万年前から今までの間、現在の京都市が海の一部だった時期があったことの名残なのだとか。「周りの地層から海洋プランクトンも見つかっているんですよ」と鈴木さん。
鈴木さんによると、平安時代から江戸時代のころは、3メートルも掘れば、どこでも地下水が湧いて出たという京都。食文化も地下水の影響を受けているのでしょうか。
「どの町家も日々の暮らしに井戸水を利用していました。作業行程で水をたくさん使う豆腐や麩(ふ)、日本酒をどこでもつくることができる環境だったんです。おいしいものをつくろうと味や技術を競い合って切磋琢磨(せっさたくま)し、食文化が発達したと考えられます」と鈴木さん。
ここ数年で、使われなくなった井戸を復活させるといった動きもある京都。地下水の価値にあらためて注目が集まりそうです。
地下水があることで発達した京都の食文化の一つが和菓子。
1803年創業の京菓子店「亀屋良長」の店先には、今も水が湧き出ている井戸があります。これは、二十数年前に社屋を現在の醒ケ井四条角に新築した際、地下を80メートル堀り、復活させた井戸なのだとか。醒ケ井通にちなんで、くみ上げた地下水を「醒ケ井水」と名付け、この水を使ってお菓子が作られています。
「シンプルな素材であるからこそ、水はとても重要です。和菓子の主な原料は豆、米粉、餅米、砂糖。井戸水を使うと、これらの香りが引き立つんです。家庭でご飯を炊くときやお茶を沸かすときにも同じことが言えると思います。これが、〝おいしい〟と言われる京の食文化の秘密かもしれませんね」と、八代目代表取締役の吉村良和さん。

井戸水の水温は常時16〜17度。「くずやちまきを冷やすときにも重宝します。醒ケ井の水は自由にくんでいただけるので、是非お越しください」(吉村さん)

渦で井戸水を表現した「醒ケ井」(864円)は、黒糖ようかんを求肥で巻いたもの



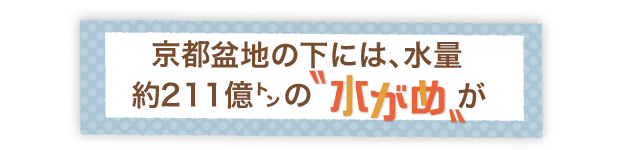

 ひと
ひと 食
食 健康・美容
健康・美容 おでかけ
おでかけ ファッション・雑貨
ファッション・雑貨 社会・生活
社会・生活 子育て・子ども
子育て・子ども 人間関係
人間関係