わが家の味をバトンタッチ!

完成したカレーをいただきます! 「真実果が作ったんか? おいしいなぁ」と目を細めていた繁男さん(中央)。これを機に、おじいちゃんに手料理をふるまう機会ができたらすてきですね
カンタンに作れて失敗がなく、来客にも出せる…。そんな理由から、山科区の橘まゆみさん宅の“テッパンメニュー”となっているのがドライカレーです。
「高校1年生の娘に伝授したい。でも、わが家の台所は狭くて2人で料理をしにくいのが悩み」
そこで今回は、まゆみさん一家の近所に住む、義父・橘繁男さん宅の台所を借り、長女の真実果さんと作ってみることに。まずはタマネギ、ニンジン、ピーマンをみじん切りにします。

みじん切りができるスライサーで、野菜をどんどん刻んでいきます。「ご飯つくるのが大変ってわかったやろ?」とまゆみさん(右)
「もうちょっと細かく刻んで」と指示を出すまゆみさんに「さっきは適当でいいって言ってたのに」と言い返しつつ、真実果さんはしっかり手を動かします。
続いては、合いびき肉と野菜を炒め、固形コンソメやカレー粉、ターメリックや数種類のハーブ、フライドガーリックといった調味料を加えていきます。どれを選ぶかは、そのときの気分次第。「いろいろ混ぜ合わせることで、どんな組み合わせでもサマになる気が。顆粒(かりゅう)だしを加えてもおいしいですよ」と言うまゆみさんに「私はバターを入れたい。だしの味とは合わなさそうやし、今日はだしはパス」と真実果さん。あれこれ相談しながら好みの味に仕上げるのも楽しい!
めいめい味付けにもこだわりがあるようです。
いつしかキッチンには食欲を刺激するスパイスの香りが。ドーナツ用の型を使ってご飯をお皿に盛り、中央の穴にカレーを入れます。見た目がかわいく、食べやすいとまゆみさんが考えました。
真実果さんによる味付けのドライカレー。「やさしくて深みのある味にできたね」とまゆみさんからのお墨付きが出ていましたよ。

5月のお祭りの日、親戚の集まる井上家の食卓にはさば寿司の大皿がお祭りの主役といった趣で鎮座。サバをおろしたときに出た骨で取っただしに千切り大根を加えて作る「船場汁(せんばじる)」とともにいただきます
京都のお祭りの日のごちそうといえば、さば寿司。「わが家では、買うよりも母が家で作るのが当たり前でした」とお便りをくれたのは下京区のHさんです。
Hさんの母・井上和子さんは、食道楽の父親がさば寿司を作る姿を子どものころから見てきたそう。でも自分で作るようになったのは、結婚後、義母に習ってからだと言います。
「そのとき、家によってやり方が違うのだと知りました。父は、サバを4~5時間ほど酢と昆布でしめたさっぱりした味を好んでいましたが、井上家では前日の夜から翌日の昼ごろまでサバをしめておき、さらに、お寿司もラップでくるんでから数本を1つの空き箱に詰め、上から重しをして、しっかりした味を楽しんでいました。私は、手に入ったサバの大きさや家族のリクエストによって、それぞれのやり方を使い分けています」
このように、今では味加減を自在に調整し、「酢飯がまろやかな風味で、サバとの一体感が最高」とHさんも絶賛するさば寿司を作る井上さんですが、そうなるまでには家族から感想を聞き、試行錯誤を重ねてきたそう。実は井上さん自身は生魚が苦手で、さば寿司も一切れをご飯ごと焼いてから食べるほどなので、家族の声が頼りだったと言います。
Hさんは、「いつか教わりたい気もするのですが、私の夫には青魚のアレルギーが。食べてくれる人が身近にいないと、作りがいがないかも…」。家族の喜ぶ顔が見たくて、自分は苦手なさば寿司を作り続けた井上さんとは反対に、自分自身のために作る一品というのも、すてきだと思います!
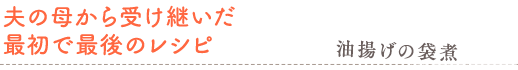
- 豚・鶏ひき肉、みじん切りにした野菜(タケノコ、ニンジン、シイタケ、大葉)、しょうが汁、酒、薄口しょうゆを混ぜて、半分に切った油揚げに詰める。ハクサイを数枚敷き、コンソメを加えた鍋にそれを入れて約20分煮込み、仕上げにごま油をたらす。結婚2年目に他界した義母から習った最初で最後のレシピ。今でもよく夫からリクエストのある一品です(kiyopy)
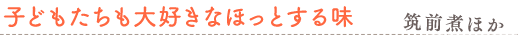
- 母は和食の煮物が得意。私は小さなころから好きな食べ物を聞かれると「お母さんの筑前煮!」と答えていました。結婚して子どもが生まれると、母は家に来て千切り大根の煮物を作ってくれるように。子どもたちもおばあちゃんの味が大好きです(れいこ)
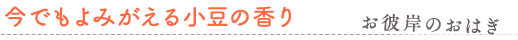
- 亡き母に教わっておけばよかったと思うのは、おはぎです。大きな鍋いっぱいに小豆を炊き、家でついたもち米にたっぷり付けて食べさせてもらった味が忘れられません。小豆を煮るあのにおいを今でも覚えています(マツイママ)
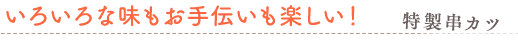
- 1本の串に、ウズラの卵、ウインナー、豚肉(牛肉)、一口大に切ったピーマン、タマネギを刺し、衣を付けて揚げます。母が私の小さなときに作ってくれて、今ではわが子の大好物。材料を串に刺すお手伝いもしてくれます(さとゆうママ)


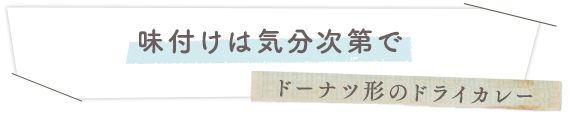
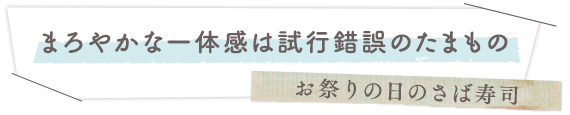

 ひと
ひと 食
食 健康・美容
健康・美容 おでかけ
おでかけ ファッション・雑貨
ファッション・雑貨 社会・生活
社会・生活 子育て・子ども
子育て・子ども 人間関係
人間関係