この地ならではの奥深さ
“京料理”ってなに?
春になれば観光客が増えますね。そんななかで頻繁に耳にする“京料理”という言葉。そういえば地元に住んでいても、それがどんなものかすっきりと説明はしにくいもの。そこで1ページ目では業態の異なる京料理店の店主にインタビュー。2ページ目では、その歴史について研究家に尋ねました。
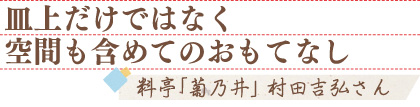

夜営業のみが当然だった時代、いち早く手軽なランチを始めたのも同店。「その時代時代で伝統文化が存続していくための工夫が必要」

春の料理。華やかな盛り付けや演出も評判です
(写真提供:菊乃井)
京都と東京に3店を持ち、さまざまなメディアでもおなじみの菊乃井。
「京都の人はお宮参りに始まり、法事や何やと料理屋を使うもの。料理屋と町の人の距離が短いんやね。だから町の人のお役に立つことが料理屋の使命と思ってます」と店主の村田吉弘さん。
「料亭は生きた美術館」と村田さん。「皿の上だけではなく、器や軸、花、家具や部屋のしつらえなど、全体が醸し出す雰囲気も含めて京都の料亭といえる。それを見る目も旦那衆に鍛えられたものです」
村田さんに京料理とは何かを尋ねると「そんなん定義なんかないよ」ときっぱり。「京都には数々の一流の日本料理店があるけど、どこも京料理を名乗ってない。みんなその店独自の料理を一生懸命出しているのを、ひとくくりにはできんよ。それなら、ロンドン料理やパリ料理がありますか?
これからは○○料理というボーダーはなくなり、受け手が決めるものになるのでは」。
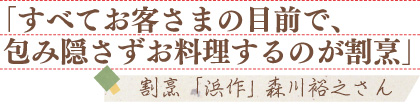

樹齢250年の尾州ヒノキの堂々たるカウンターに、毎夜立ち調理をする森川さん。森川さん自身が講師を務める料理教室も開講、女性に人気です

大ぶりの造り鉢に豪快に盛られた、浜作名物のタイのお造り。「明石や淡路島など近海産の天然ダイの中でも、状態の良いものを選んでお造りにしています」(森川さん)
昭和2年、日本で初めての板前割烹(かっぽう)として、祇園町で創業した浜作。
「当時の高級料理は、あらかじめ用意されたものをお座敷でいただくのが通常でした。そんな時代に、私の祖父・森川栄は、即日入手した新鮮な材料をお客さまにお見せしてご希望をお伺いし、板前がカウンターで調理する“割烹”を生み出したのです。これは当時の日本料理界にとって革命的な出来事でした」(3代目主人・森川裕之さん)。その衝撃は、開店日の様子が新聞にも報じられるほど大きなものでした。
食通の間でも評判となり、川端康成や谷崎潤一郎ら文豪や著名人も通い詰めたといいます。
10年前に、八坂神社鳥居前に本店を移し、新装。割烹本来の伝統を守る浜作の料理を求めて、全国からグルマンが訪れます。
「祖父・父から3代変わっても、割烹の“当意即妙の精神”は変わらずに伝えていきたいです」
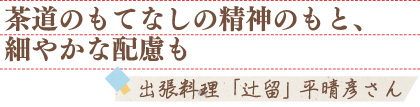

「通常の料理店と異なり夜の仕事はあまりありません。代わりに朝が早いですね」(平さん)。1月の初釜の時期は毎日数百人分を作るのだとか!

春らしく、ご飯には桜の花を散らして(写真提供:辻留)
明治35年創業の辻留。京都店は現在も、創業当時と同じ出張料理専門です。初代・辻留次郎さんの代から、裏千家の“お台所”を任される名店です。
出張料理が仕出しと異なるのは、仕上げを出先の台所を借りて行う点。根底にあるのは“温かいものは温かく”という茶のもてなしの心です。「造りは直前に切り、ご飯も現地で炊きます」(店主・平晴彦さん)
茶会のほか、冠婚葬祭の場や大文字鑑賞会などにも出張。「趣旨はもちろん各お家の道具などが異なるので、きめ細かいご要望にお応えできるよう事前に打ち合わせし、献立や食器を決めます」
お茶の世界で季節感は大原則、と平さん。「旬とずれた食材を使うことはありえません」。着物を汚さないよう、取り回しのしやすいように盛り付けるなどの配慮も。「炊き合わせは汁の散りやすい青菜を省いたりします」
出されたものは残さない決まりのため、食用ではない飾りも使いません。「お茶の世界は合理的なんですよ」


 ひと
ひと 食
食 健康・美容
健康・美容 おでかけ
おでかけ ファッション・雑貨
ファッション・雑貨 社会・生活
社会・生活 子育て・子ども
子育て・子ども 人間関係
人間関係