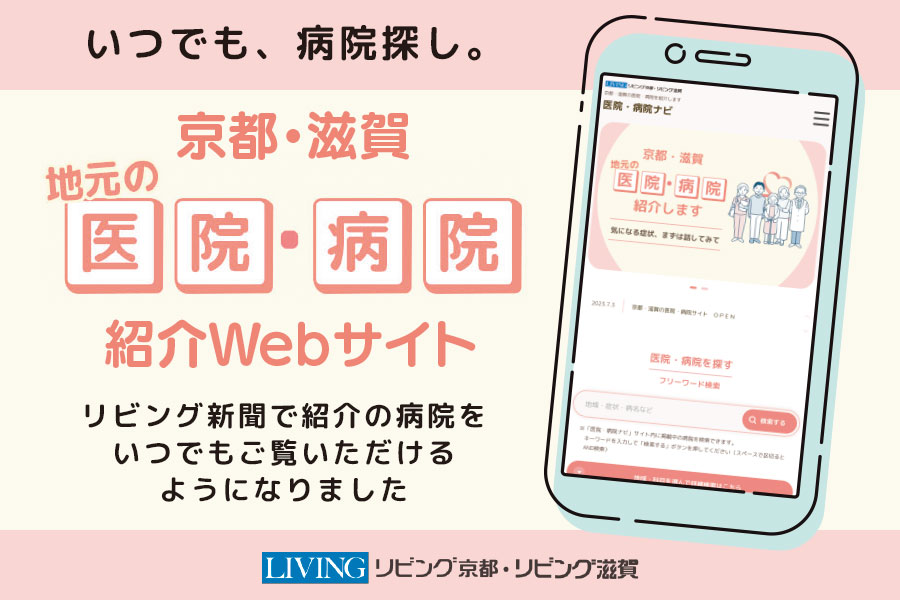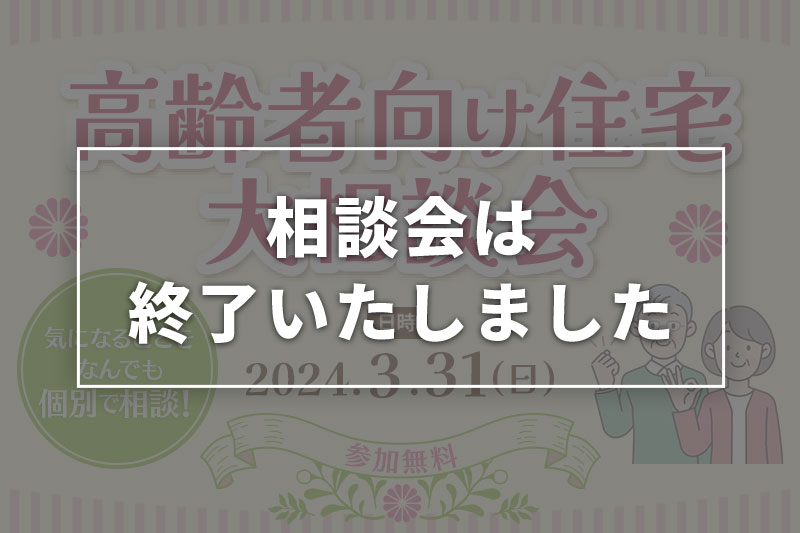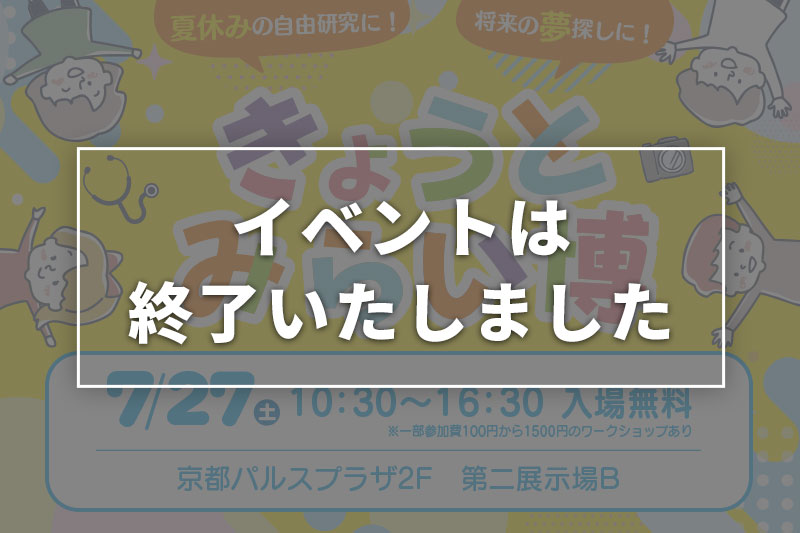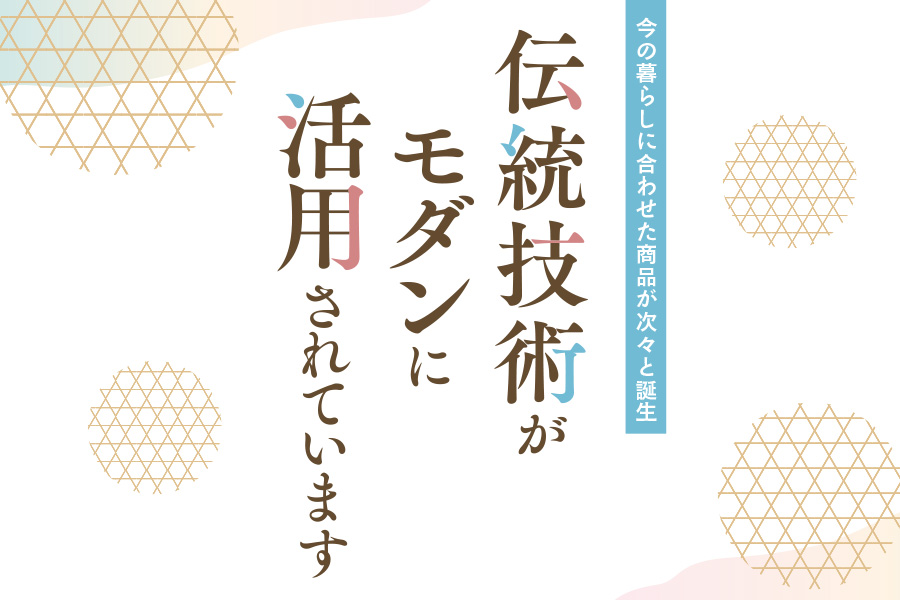
京都に息づく数々の伝統産業。脈々と受け継がれる技術を生かしながら、時代にあわせた新たな製品を生み出しています。歴史あるお店で作られた新商品を、作り手の思いと共に紹介します。
撮影/岡森大輔、深村英司ほか
京都市では約1万3000人が伝統産業に従事
「京都の伝統産業の特徴として、まずは業種の多様さが挙げられると思います」とは、京都精華大学伝統産業イノベーションセンター長の米原有二さん。
京都府下で「伝統工芸品」と呼ばれるものは、国が指定するもので17品目、京都市が条例で「伝統産業品」に指定するもので74品目あるそう。西陣織や京友禅、仏具など、多岐に渡ります。
さらに、京都市の人口約140万人のうち、約1万3000人が伝統産業従事者といわれているとか。約100人に1人と考えると、身近なものに感じますね。
「伝統工芸の多くは、細かい分業制。昔は物流が発展していなかったため、同業が集まって職住一体に生活をすることが多く、町全体が工場のような役割を担っていました」。
西陣や清水などは、そうして伝統産業で名高い地域となったそう。
注文制作ならではの魅力や課題も
「また、伝統産業はいわゆる注文制作が主。京都は生産地でありながら、昔から全国でも有数の消費地でもあり、目の厳しい使い手が身近にいました。そういう客に応えて制作するうちに、技術が高まっていったのでしょう」
ただ、注文制作であることから、現代では消費者が気軽に購入できるような店頭に出回りづらいという課題も。
「手仕事が多い伝統工芸の品物は、たとえ100年前の商品であったとしても、修理できる場合が多いんですよ。そういったことまで知ると、より魅力を感じてもらいやすいのでは」

まとった香りを長く保つ扇骨の特性から着想

大西常(つね)商店のルームフレグランス
下京区・松原高倉にある町家に店を構える「大西常商店」。1913年に創業以降、扇子の製造・販売を行っています。
同店で新たに開発したのが、扇子の骨組みを使ったルームフレグランス「かざ」。「『かざ』とは、香りを意味する京ことばです。扇子用に薄く加工された竹・扇骨は、まとった香りを長く保つ特性が。それを応用した商品で、透かし彫りの細やかな文様を取り入れています」と話すのは、同店四代目店主の大西里枝さん。
竹製の骨組み部分は、加工、かなめ打ち、裁縫とそれぞれ専門の職人の手で作られているそう。
開発のきっかけは、お客さんからの言葉だったそう。「代替わりして間もない頃、扇子の香りが長く続くのは何故かと聞かれて。自分では当然と思っていましたが、はっとしました」
冬季は扇子の需要が少ないため、一年中販売できる商品をと模索していたこともあり、このフレグランスを開発するに至ったのだとか。
「実は、香りと扇子には昔から深い関係が。恋人に香りをまとわせた扇子を送り、その香りで自分を思い出してもらうという使い方もされていたんですよ。そんな扇子の文化も、商品を通して知ってもらえたら」

漆を使うことで、口当たりが優しく、抗菌性もアップ

COCOO(こくう)のタンブラー
「ステンレスの容器の金属臭を打ち消すコーティング材はないかと探し、出合ったのが漆でした」と話すのは、日用品のものづくりを行う「COCOO」の広報担当・前田愛花さん。
漆を使った製品の開発・販売を手がける「佐藤喜代松商店」と共同で誕生させたのが、「漆タンブラー『KISSUL(キッスル)』」です。
漆は金属に塗ると剥がれやすい性質がありましたが、古くから船に使われていた焼き付けの技術を用いてタンブラーの内側のステンレスにコーティングしたのだとか。


「漆タンブラーは、ステンレスの保温性・保冷性はもちろん、抗菌性にすぐれ、丈夫で食洗器にも対応可能。傷が付いても、漆で修理しながら使い続けられます」
カラーは5種類。「佐藤喜代松商店には、100色以上の色漆がそろっています。その中から厳選しました」
また、昨年新たに「紙漆カップ『KOMLA(コムラ)』」を制作。「紙に漆を繰り返し塗ることで、水にも耐えられるように。〝洗える紙コップ〟が生まれました」
樹液を原料とする漆は、土に還るサステナブルな素材としても注目されているとか。
「古くからある素材ですが、さまざまな可能性を秘めています。ぜひ、多くの人にその魅力を感じてほしいです」
プロが使っていた焼き網を一般家庭用に

金網つじのセラミック付き焼き網
縁起が良い亀甲模様を描きながら一つ一つ手作業で銅線を編み上げて作る、京金網。その専門店「金網つじ」は、高台寺にほど近い、一年坂に店舗を持ちます。
「当店のセラミック付き焼き網で食材を焼くと、外側はサクッと、中はふっくらとした仕上がりに。これは、セラミックが持つ遠赤外線効果を活用しているためです」とは、二代目店主・辻٩}さん。
「元々、当店で扱っていた、昔ながらのセラミックを付けた焼き網はプロ用に卸していた製品でした。家で父親が食パンを焼くのに使っていたのですが、それがおいしくて。広く販売できないかと思ったのがきっかけです」
洗えないという致命的な欠点があった従来品を改良するため、「ファインセラミック」という素材を探し出したといいます。洗えて、なおかつ遠赤外線効果も従来より高いのだそう。焼き網には耐久性のあるステンレスを採用。丈夫なステンレスを同店の技術で編み上げます。
「焼き網とセラミック網の二重構造になっていて、使用後は丸洗いが可能です。大きさも家庭で使いやすくよう、コンパクトに。コンロの火と網の距離を考え、台の高さも調整しました」
伝統工芸といえど、私たちが作っているのは日々の道具であり、今使われないと意味がない、と話す辻さん。
「昔と今では食事の内容も暮らし方も異なります。職人はお客さんに合う商品を作り続けるのが仕事。常に想像を超えてくる未来に向けて、変わっていくことを楽しみたいですね」

こんなアイテムにも注目を

復元させた製法で、きめ細やかな表面のコースターを実現
京瓦にシルクスクリーン印刷を施した、「浅田製瓦工場」の「京瓦コースター」(4400円)。表面をきめ細やかにするため、〝本ウス〟という瓦の製法を復元させたといいます。さらに、水を弾くように作られている瓦を、焼成方法や温度を工夫して吸水性のあるコースターに。

掛け軸用の表装裂を使って軽く、華やかなワインバッグに
金襴緞子(きんらんどんす)の美術織物を扱う「鳥居」が考案した華やかなワインバック「金襴 鳥の子 唐花」(3300円)は、掛け軸用の表装裂(ひょうそうぎれ)を使用。軽さとデザイン性を優先し、裁断面は縫製していないそう。簡単に包装ができ、繰り返し使えるのもポイント。

竹のしなやかさと自然の温かみを生かした指輪
天然素材ならではのやさしいつけ心地が魅力の「長岡銘竹」が手がける「竹の指輪」(1650円)。金属アレルギーの人に喜ばれているのだとか。しなやかさが特徴の竹を丁寧に割ってはぎ、細い棒状の竹ひごにしてから、一つ一つ編んで指輪にしています。
(2025年2月22日号より)
最新の投稿
おすすめ情報
- カルチャー教室
- アローズ
- 求人特集
- 不動産特集
- 京都でかなえる家づくり
- 医院病院ナビ
- バス・タクシードライバー就職相談会in京都
- 高齢者向け住宅 大相談会
- きょうとみらい博