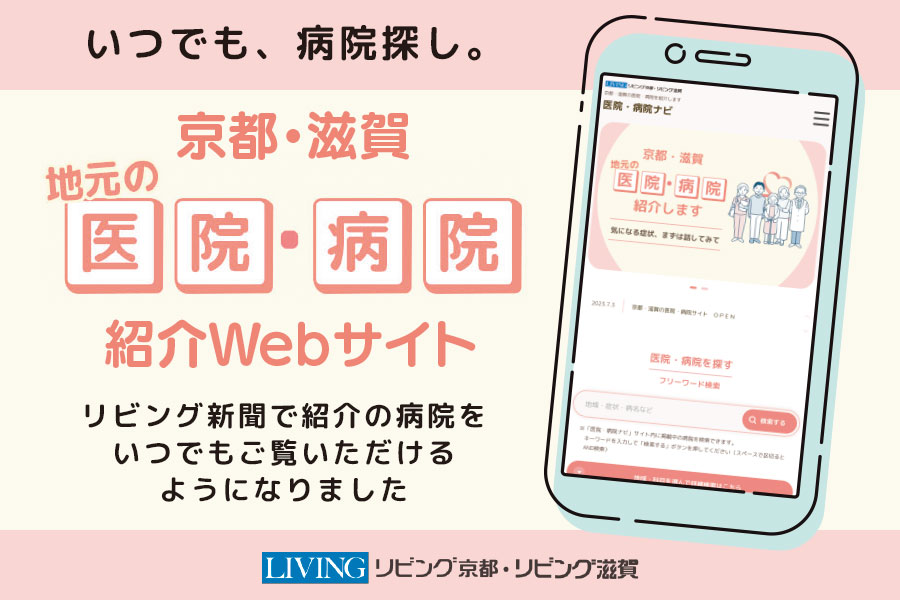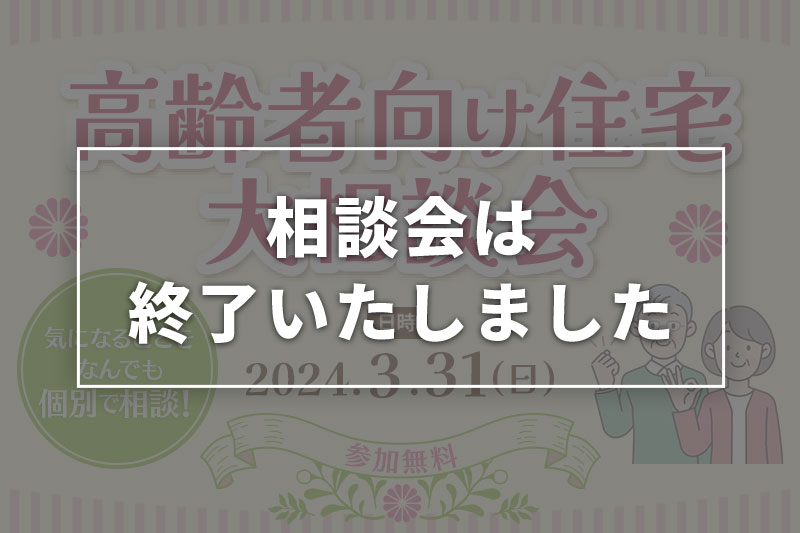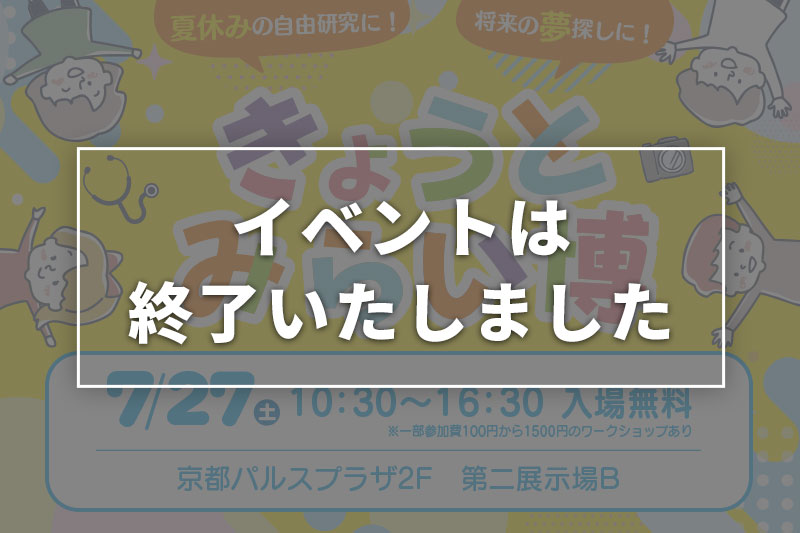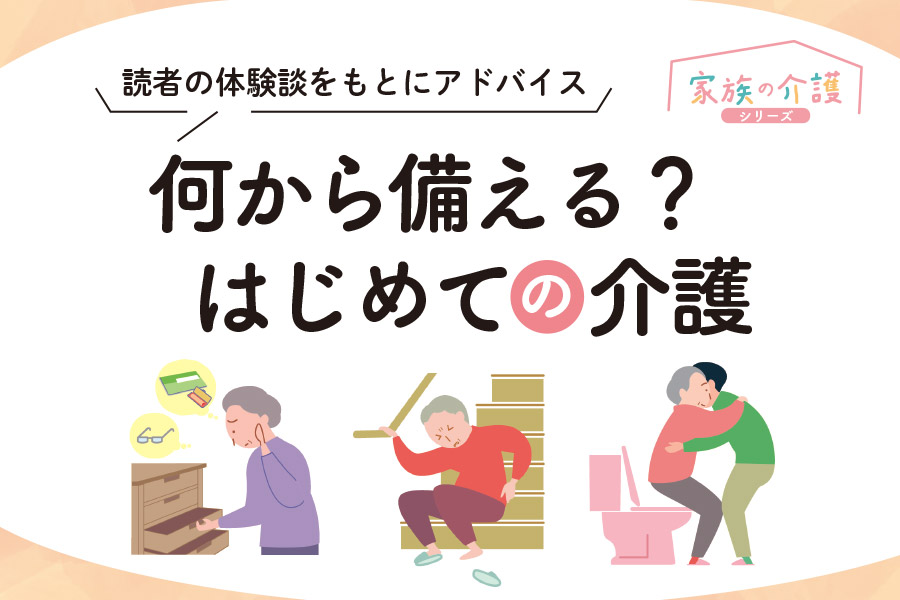
家族の介護は、実際に直面するまでイメージが掴めず、備えが不十分になることも。そこで、読者の体験談を踏まえながら、介護が始まる前、始まったときに何をすればいいか、専門家にアドバイスをもらいました。
※2024年11月にリビング読者にアンケート。有効回答数820、本文()内はイニシャル・年齢 イラスト/オカモトチアキ
親が80代、子が50代のときに経験する人が多数
介護経験がある読者に、親の介護が始まった時期を尋ねると、半数近い人々が、親が80代、子が50代のタイミングという結果に。また、そのきっかけには、認知症の発症、転倒・骨折、老衰、脳血管疾患などが挙げられました。
「介護は、体の衰えや認知症などで徐々に必要になるケースと、けがや病気がきっかけで急に必要になるケースがあります。特に突然始まる場合、家族の準備や心構えができておらず、困り果てて相談に来る方も多いですね」
そう話すのは、「高齢者情報相談センター」の内山貴美子さん。京都府内で暮らす高齢者とその家族の生活相談を受けています。
「親の介護を意識する年齢になったら、まずは友人や親族、著名人の体験談を積極的に見聞きしてみましょう。自分は介護の当事者という意識を持つことが、備えの第一歩になります」
下に、読者の体験談をいくつか紹介しています。
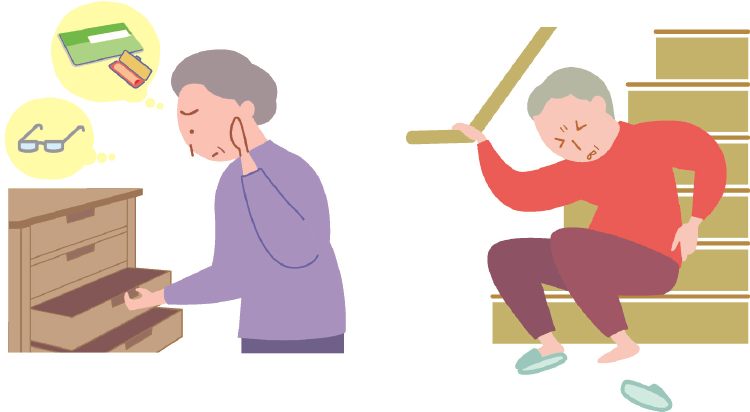
【Q】親の介護が始まった時期は?
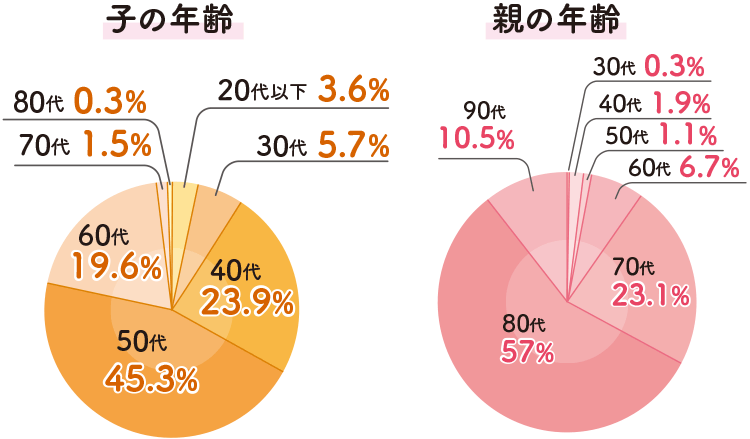
【Q】介護を始めた理由は?(複数回答可)
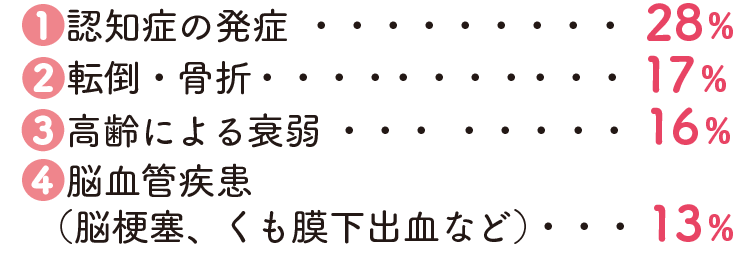
読者が体験した介護の始まり
●突然の病気やけがで
- 前日まで元気だった父が朝、(脳卒中で)半身不随になり救急搬送。半年入院し、リハビリして帰ってきました。車いす生活になり、要介護4に(Kさん/当時子51歳・親90歳)
- 家事中に倒れ、大腿骨を骨折。手術とリハビリで自力歩行まで持ち直したが、杖と手すり頼みで外出が難しくなり、そのうち認知症の症状も出てきた(Wさん/当時子55歳・親83歳)
●徐々に進行して…
- 運転免許の更新に行った親が夕方になっても帰ってこない。捜索願いを出したら、深夜に警察署から『保護したので迎えに来てほしい』と連絡が。認知症でした(Iさん/当時子48歳・親78歳)
- 自ら自立型の施設に入所していましたが、以前から骨粗しょう症があり、背骨を圧迫骨折。私は施設に通って介護しました(Tさん/当時子58歳・親87歳)
- 遠方に住む父から「書類関係や身の回りのことができなくなってきたので帰ってきてほしい」との訴え。母とも相談の上、夫婦で実家に引っ越しました(Oさん/当時子59歳・親84歳)
- (親が)青信号の間に横断歩道を渡りきれなくなったとき、一人で出かけるのは危険と感じた(Tさん/当時子50歳・親78歳)
介護前から頼れる相談窓口やボランティアをチェック
読者が介護をする際に困ったことについても、内山さんにアドバイスをもらいました。これから始まるかもという人は参考に。一番多かったのは、「どこに何を相談したらいいかわからなかった」(Tさん・62歳)という声。
「高齢者の介護や保険、医療、福祉に関することは『地域包括支援センター』で相談できます。困りごとや悩み、不安を伝えることで、適切な制度やサービスを案内してもらえます」
介護が必要になったときの大まかな流れを、下記で紹介します。
続いて多かったのは「(同居する親を)昼間一人にするのが心配だった」(Oさん・66歳)というもの。仕事や遠距離で暮らしていることが理由で見守りができないときは、地域のボランティアに頼る方法もあるそう。
「自治体には、厚生労働大臣から委託され、担当地域の福祉の相談・援助を行う〝民生児童委員〟が配置されています。また、京都市には、主に一人暮らしの高齢者を訪問し、安否確認を行ってくれる〝老人福祉員〟という独自制度もあります」
親が住む地域の担当者を知りたい場合、各自治体に問い合わせを。
「いずれも介護が始まる前から利用できます。前もってつながりを持っておくと、もしものときの連携がスムーズです」
さらに読者の体験談をいくつかピックアップし、アドバイスをもらいました。
要介護認定の流れ
相談
要介護者が住む地域の「地域包括支援センター」へ。市役所・区役所・支所(保健福祉センター)でも対応。本人・家族の相談を受け付けています。
要介護認定の申請
介護保険サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。申請は、市役所・区役所・支所の窓口へ。地域包括支援センターなどに申請代行を依頼することもできますが、申請書類は本人または家族が用意する必要があります。
※京都市をはじめ、一部ではオンライン申請に対応した自治体もあり
審査
調査員による家庭訪問、かかりつけ医の意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門家による審査・判定が行われます。
認定
認定結果は、原則申請から30日以内に通知されます。要支援1〜2、要介護1〜5と、要介護度は7段階。それぞれに応じた介護保険サービスを利用できます。
ケアプランの作成
居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーに、自宅での介護サービス・介護予防サービスのケアプランを作成してもらいます。
サービスの利用
利用できるサービス量や利用限度額、自己負担額は要介護度や所得により変わります。事前申請・審査が必要なものも多いので、早めの利用検討を。
要介護認定に非該当の65歳以上の人も、一般介護予防事業(原則無料)を受けられる場合があります。
体験談❶仕事や育児と、介護の両立は精神的にも体力的にも大変だった
「介護に専念するため離職すると、50代以降、再就職が難しいという現実が。収入減は介護者の老後にも影響するため、慎重に検討したいところです。そこで注目したいのが、「育児・介護休業制度」で定められた、仕事との両立支制度。2025年4月に法改正が施行され、勤続6カ月未満の従業員も介護休暇(※)の取得対象に。また、事業主は、制度の社内周知・相談体制の整備が義務化。介護中の従業員のテレワーク措置が努力義務になります。両立支援制度はほかにも。制度の動向をチェックしながら、上手く活用していきましょう」
※通院の付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせなどを行うために年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで、1日または時間単位で休暇を取得できる制度
体験談❷介護の情報、知識があまりありませんでした。事前に、学ぶことができていればと思った

「自治体では、介護知識・介助技術を学べる、市民向け講座が行われていることも。たとえば京都市の『介護実習普及センター』は、本人や家族など市民を対象とした『やさしい介護講座』を開催しています」
体験談❸親が病気やけがで入院したとき、転院先や退院後の介護施設を探すのに苦労した
「病院に入院できる期間はおむね3カ月といわれています。介護施設は入所待ちですぐに転居できない場合や、対象となる要介護度が定められている場合も。日頃から施設の情報を集め、本人の要望に合うサービスや価格帯の施設の見当をつけておきましょう。要介護認定の申請は入院中から可能。ただし、本人の回復具合、家族の事情によってその後の介護の方針も変わってくるため、申請は退院のめどが立ってからがおすすめです」
読者が感じた備えの大切さ
介護を経験したことで感じた「備えておいて良かったこと、後悔したこと」を紹介。
- 介護施設の情報。施設によってサービスに差があるので、利用者の評判が参考になりました。施設に出入りしている美容師さんの話も役立ちました(Oさん・74歳)
- 事前に要介護認定を受けていたこと、エンディングノートを作成する目的でお金の情報を聞いておいたこと。説得するのにかなり時間がかかりましたが…(Iさん・56歳)
- 母は何年も前から準備していた様子。介護の相談窓口、普段お世話になっている病院や施設などの情報を常に更新していました(Kさん・78歳)
- 父母の通院に早めに付き添えばよかった。本人は「心配ない」と言っていたが、実際は母が認知症と診断されており、父も介助が必要な状況だったと後からわかった(Tさん・62歳)
- できること、できないないことをハッキリとさせておけばよかった!無理して結局、自分が身体を壊してしまった(Hさん・64歳)
日頃のコミュニケーションで変化に気付いて
介護の始まり方は家庭によってさまざま。しかし、少しでも早く親の変化に気づくことができれば、職場や専門機関にも早めに相談できます。
「大切なのは、親の生活習慣や好みなどを把握しておくこと。たとえばきれい好きだったのに掃除をしなくなった、身だしなみに気を遣わなくなった、料理の味付けが変わった。こうした変化は認知症の可能性があります。日頃からコミュニケーションをとり、本人が元気なうちに介護にまつわる希望も聞いておきたいですね」

〈 教えてくれたのは 〉
高齢者情報相談センター
センター長 内山貴美子さん
(2025年1月25日号より)
最新の投稿
おすすめ情報
- カルチャー教室
- アローズ
- 求人特集
- 不動産特集
- 京都でかなえる家づくり
- 医院病院ナビ
- バス・タクシードライバー就職相談会in京都
- 高齢者向け住宅 大相談会
- きょうとみらい博