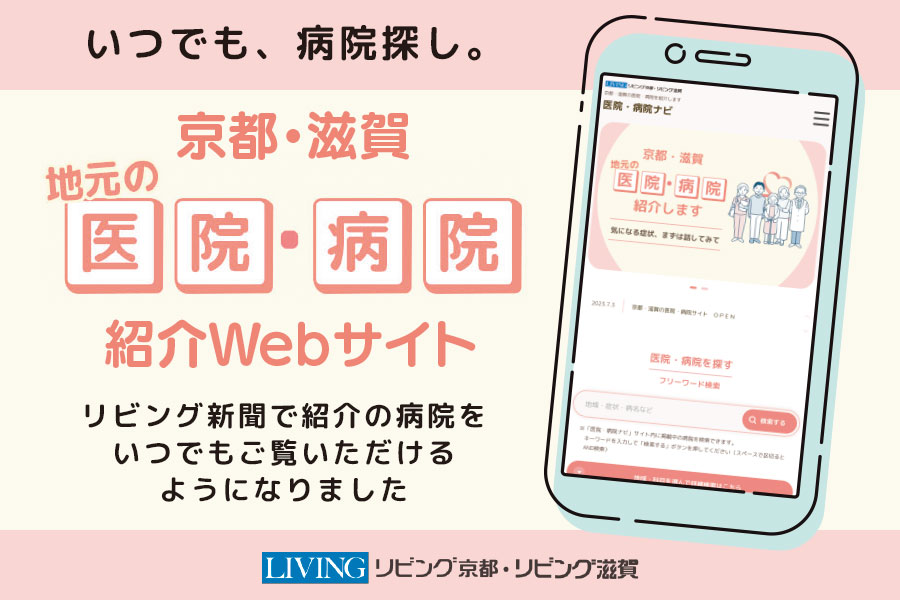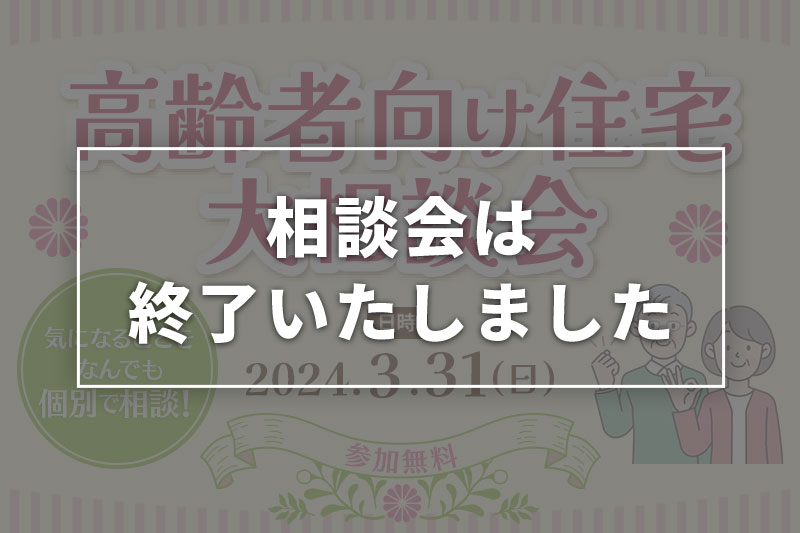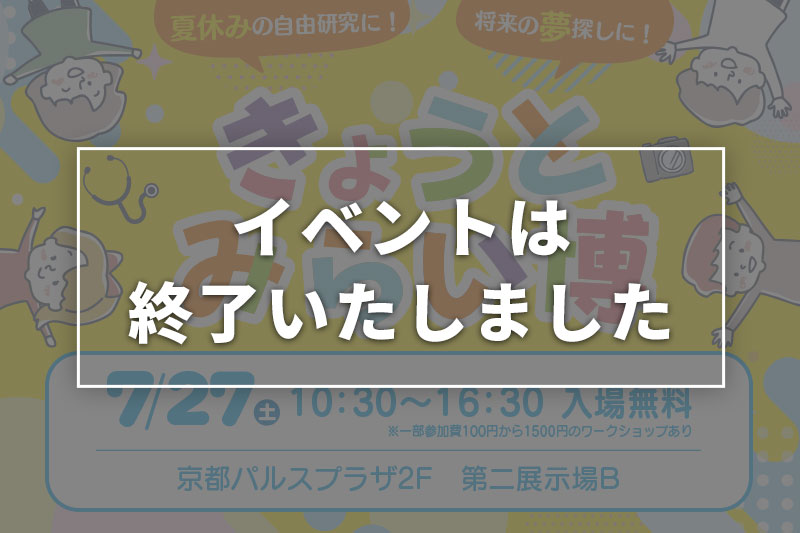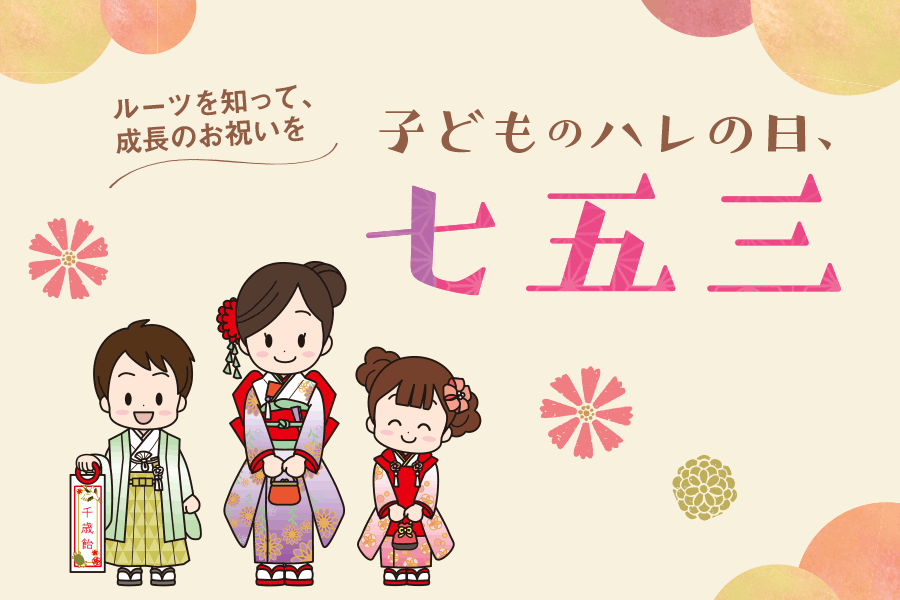
秋になると、晴れ着に身を包み、千歳(ちとせ)あめを手にした子どもの姿を見かけますね。知っておきたい七五三の基礎知識を、京都の文化に詳しい「らくたび」の若村亮さんに教えてもらいました。
最近では、晴れ着で記念撮影をしたり、食事をしたりと、「思い出に残るような七五三にしたい」と考える人が多いよう。祖父母も含めた3世代で、お祝いをするケースも見られます。
本来、七五三とはどのような行事で、何をするものなのでしょうか。由来やお参りの仕方を知り、子どもの成長を祝いましょう。
七五三の始まり
昔は幼いころに命を落としてしまう子どもが多かったため、無事成長することを願い、神様に祈りました。それが七五三の起源といわれています。
江戸時代になると、武家を中心に3歳・5歳・7歳の各年齢に合わせて儀式をするように。明治時代には一般庶民にも広がり、年中行事として定着していきました。
男女の年齢の違い
江戸時代、3歳で男女ともに行ったのが、「髪置き(かみおき)」の儀式。それまでそっていた髪を伸ばし始めるものです。
「袴着(はかまぎ)」は、5歳の男児が成人男性と同様にはかまを身に着ける儀式。7歳の女児は、着物を留めていたひもを解いて帯を締める「帯解(おびとき)」を経て、大人の仲間入りを果たしました。
この名残で、男児は3歳と5歳(3歳は省く場合も)、女児は3歳と7歳にお祝いをしています。かつては数え年でしたが、今は「分かりやすいから」といった理由で満年齢を選ぶ傾向にあります。
参拝する場所
昔は地域の守り神である産土(うぶすな)神に参拝していました。現在は好きな神社を訪れる人が増えています。
時期は11月15日の前後1カ月が目安。子どもが成長したことの感謝や報告をしに、神社へお参りしましょう。
千歳あめの意味
江戸時代に発祥したという千歳あめ。「千歳」という名称や細長い形に長寿の願いが込められたあめが、七五三と結び付きました。
袋に描かれているのは松や鶴、亀など。縁起のいい絵柄からは、「長生きできるように」との思いが伝わってきます。
お祝いをする時期
11月15日が七五三の日とされています。
旧暦の11月は、収穫を終えて実りに感謝する時期。11月15日は旧暦で満月に当たり、収穫祭と合わせて子どもの成長を祝っていたとの説があります。

<教えてくれた人>
若村亮さん
「らくたび」代表取締役。全国で実施されている京都学講座の講師として活躍中です
http://rakutabi.com/
(2020年10月3日号より)
最新の投稿
おすすめ情報
- カルチャー教室
- アローズ
- 求人特集
- 不動産特集
- 京都でかなえる家づくり
- 医院病院ナビ
- バス・タクシードライバー就職相談会in京都
- 高齢者向け住宅 大相談会
- きょうとみらい博