感じ取りたい、警戒心の発動ポイント
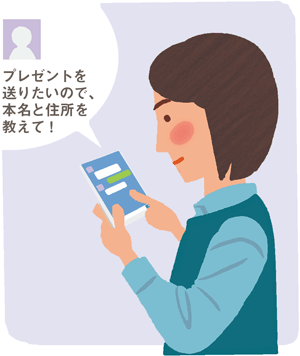
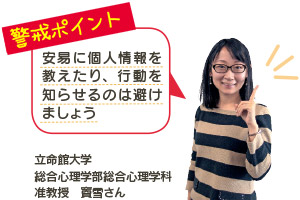
フェイスブックやツイッターなど、SNSについて教えてくれたのは、立命館大学総合心理学部総合心理学科の准教授・竇(とう)雪さん。相手の顔を見ずにやりとりできる分、警戒心が必要なシーンがあるといいます。
「例えば、誰でも見られるSNSのページで『家族旅行に来ている』と投稿した場合は、空き巣被害に遭うリスクが高まります。帰ってきてから投稿する、特定の友達だけが閲覧できる非公開ページを活用するなど、工夫するといいですね」
SNSを通じて個人情報を知られ、嫌がらせを受けるといったトラブルもあります。
「良い人だと思っても、素性が分からないうちから警戒を解くのは危険。住所や名前などの個人情報を教えたり、1対1で会うのは避けましょう」
SNS上の顔写真は、合成して悪用されるケースも。子どもにとっては、いじめに結び付くことがあるといいます。
「アメリカでは、顔写真だけで日本のマイナンバーのような番号を特定する技術が今後生まれるといわれています。個人情報を盗み、悪用する犯罪につながりますね。日本でもいずれ起こると考えておいた方がいいかもしれません。
とはいえ、SNSは今では身近なコミュニティーツール。行動範囲が狭くなりがちな高齢者にとっても、交流のきっかけになっています」
上手に使いこなせるかは、警戒心の持ち方次第といえそうです。
写真を投稿するタイミングや
公開範囲に気を付けます


- ●子どもが小さいとき、公園で知らないおばあさんがお菓子をくれました。ですが、「もしかして毒入りかも」などと考えたら食べさせられず…。きっと親切だったのだろうと、疑ったことを後悔しています(IA・50歳)
- ●会員制交流サービス(SNS)に身元が分かるような写真やコメントを載せている人の多さに驚きます。何かあったらと思うと、私は投稿できません(KA・50歳)
- ●母は警戒心が強いタイプ。大手の通販会社を利用しているのに、「怪しいのに何で買うの?」と言われます。そんなに疑わなくても、と思うのですが(りのあやママ・56歳)
だまされないためには、周囲との関係づくりも大事
警戒する、信用する。その心の動きにはさまざまな要因があるよう。
京都橘大学健康科学部の准教授・前田洋光さんは、「警察、消防署、市役所など、権威性のあるところからの情報は、どうしても信用しやすくなります」と指摘します。
「特殊詐欺はこの心理を利用しています。また、不安を解消するためならお金を払うというリスク回避の心理も、だまされる原因の一つ。『子どもが会社の資金を使い込んだ。すぐに返金するなら警察には言わない』といったうそを信じやすくなります」
ですが、人を疑うのはやはり抵抗もあります。

京都橘大学健康科学部
准教授 前田洋光さん
「例えば高齢者の見守り活動。親切な人に対し、『信用させて金品をだまし取るのでは』とは思いたくないですよね。善意には感謝しつつ、金銭面は一切他人に任せないと線引きするといいのでは。〝疑う〟ではなく、始めからルールにしておくのです」
前田さんが大事だというのが、身近な人との関係づくり。
「人は誰かと関わりたいという思いを持つもの。孤独だと、近付いてきた人物が少々怪しくても信用したくなります。友人や地域の人と、何かあったときに相談できる関係を築けるといいですね」
ネットショッピングのトラブル
- ●京都市消費生活総合センター ※京都市内在住の人が対象
- ☎075(256)0800 ※月〜金、午前9時〜午後5時
- ●消費者ホットライン
- ☎188(いやや)
特殊詐欺やSNSのトラブル
- ●京都府警察 警察総合相談室 ※緊急の場合は110番へ
- ☎#9110 または ☎075(414)0110
※月〜金(祝日・年末年始を除く)、午前9時〜午後5時45分

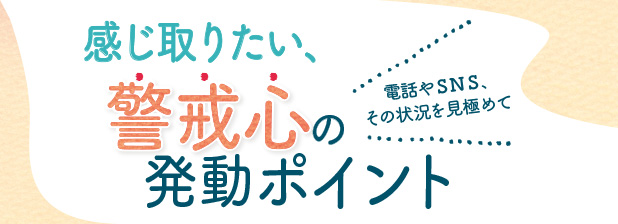

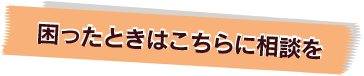
 ひと
ひと 食
食 健康・美容
健康・美容 おでかけ
おでかけ ファッション・雑貨
ファッション・雑貨 社会・生活
社会・生活 子育て・子ども
子育て・子ども 人間関係
人間関係