別れの後に見つけたこと
大切な人を亡くしたり、病気によって以前の健康や仕事を失ってしまったり―。
今回は、こうした何らかの「別れ」を経験した人たちの物語です。
その経験によって、新たに見えてきたこととは何だったのでしょうか?

知人から「作り方を教えて」と言われて始まった、岡本さんの教室。この日は、着物をリメイクして作るドレスに挑戦していました
葬儀やお墓などについて生前から考える「終活(しゅうかつ)」が話題になっていますが、みなさんは最期にどんな服を着て旅立ちたいか、考えたことがありますか?
読者の岡本文香さん(63歳)は、この秋から自宅で“エンディングドレス”を作る教室を始めています。きっかけは、2年前、姉の弘美さんが、持病を急変させて亡くなったことでした。
「母の介護を一緒にしていた姉が、母より先に逝くなんて…。納棺の際には本人が用意していた着物を葬儀社の方が着せてくれましたが、パジャマの上からだったため胸元がスッキリせず、帯も一重だけ巻いただけで、結ぶことはできませんでした」

ブラウス、パンツ、コサージュ付きのシルクのボレロ、布製のシューズからなるエンディングドレス
長年服飾関係の仕事をしてきた岡本さんは、この出来事を機に、着せ付けが簡単で華やかなエンディングドレスを、自分と母・糸子さん用に製作。糸子さんが93歳で永眠したときには、そのドレスを着せて見送ったそうです。
「姉からは、『死は年齢に関係なく誰にでもやってくる』と教わりました。ならば死を怖がらずに受け入れたいと思ったし、母のドレスを作る中で、別れに対する心の準備ができました。すると、いま生きていることへの喜びも実感できたんです」
大切な家族との別れが、死から目を背けないことの大切さを教えてくれたのですね。

松永さんが理事長を務め、視覚障害を持つスタッフも働く「町家カフェ・さわさわ」(寺町通丸太町下ル)の前で。「目の不自由な人が笑顔で集い、仕事を学ぶ場になればうれしいです」。
松永さんのホームページ=http://www.nobuya.org/
「自分の目に異変を感じたのは35歳過ぎ。いつも目の前に濃い霧がかかっているような感じで、電柱にぶつかることも増えました。それでもまだ自分が失明するとは考えていなかった。信じたくなかったんやろうね」
こう振り返るのは、西京区の松永信也(のぶや)さん(56歳)。松永さんは子ども時代に「網膜色素変性症」という病気を患い、40歳のころ、その悪化により両目の視力を失います。その結果「天職」だと信じていた児童福祉施設での仕事を辞めざるを得なくなりました。
「何もする気になれず、自宅に閉じこもっていた」という松永さんの心に変化が訪れたのは、その1年後。「落ち込むことに飽きてきたんです(笑)。1年たってようやく、見えることをあきらめられるようになった。すると、『もう一度外を 歩きたい』という欲求が湧いてきたんです」
その後、松永さんは京都ライトハウスで白杖を使った歩行訓練を受けます。最初は周囲の視線が気になったそうですが、次第に「階段はどこにありますか」「バスの乗降を手伝ってください」と自分から声がかけられるようになったとか。「すると次は『働きたい』という目標ができました」

松永さんの講演は、小学生から一般の人を対象にしたものまで内容はさまざま(写真提供/松永さん)
松永さんは前職の人脈などを生かしつつ、いくつかの仕事を経験し、現在は講演活動や著述業を中心に活躍中です。
「僕は視力を失い、『見える』世界とは別れましたが、同時に『目の不自由な人は不幸だ』という思い込みとも別れました。いまは知らない誰かに声をかけ、助けてもらいながらあちこちに出向く毎日で、年間1500人以上の人と言葉を交わしています。こんな人生も面白い、と思うんです」



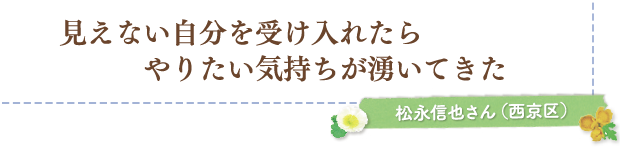
 ひと
ひと 食
食 健康・美容
健康・美容 おでかけ
おでかけ ファッション・雑貨
ファッション・雑貨 社会・生活
社会・生活 子育て・子ども
子育て・子ども 人間関係
人間関係